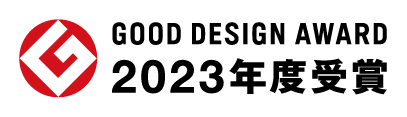森の香りで人と自然をつなぐ。HIKOBAYUが届ける「今、ここ」にある豊かさ
ニセコ町事業者の想い
文:本間幸乃 写真:斉藤玲子
木々の間から漏れる陽の光を浴び、土や緑の勾いを嗅ぐ。澄んだ空気に思わず呼吸が深くなるーーそんな森の中の体験を「香り」を通して届けているのが、クラフトアロマブランドHIKOBAYU(ヒコバユ)です。「森と人をリンクする」を合言葉に、北海道ニセコ産トドマツの精油を軸にしたアロマオイルの製造を行っています。
製品への想いとこれまでの歩みについて、代表・澤田佳代子さんにうかがいました。

ニセコのトドマツに新たな命を吹き込む
切り株や伐った木の根元から生えてくる若い芽を表す「蘖(ひこばえ)」。その自然現象に由来する屋号には、「一度役割を終えた命に、新たな価値を吹き込みたい」という思いが込められています。
「アパートの一室から始めた」という精油づくり。なぜ「トドマツ」の香りに着目したのでしょうか?

ーー「トドマツ精油」をつくり始めた経緯を教えてください。
澤田:元美容師である夫のアイデアがきっかけです。シャンプー開発に携わった経験から、「ニセコならではの香料」を作ったら面白いんじゃない?と。
精油の原料となるのは伐採後に残る枝葉です。「林地未利用材※」と呼ばれる枝葉は、肥料として森に放置されるか、産業廃棄物として処理されるのが通常です。
トドマツは北海道にしかない樹木ですし、香りも良く、オイルも抽出しやすい。私たちの手を介すことで、「新しい価値」として再生できるのではないかと、精油づくりを始めました。
※林地未利用材とは、森林整備の際に伐採された木材のうち、製材等に利用できない細い木、枝、幹、根元などの未利用のまま山林に残される木材のこと。
ーー精油の抽出はどこかで学ばれたのですか?
澤田:水蒸気蒸留※という古くから伝わる方法を、試行錯誤しながら独学で習得しました。
蒸留器も夫が設計した手作りです。初号機は当時住んでいたアパートの一室にあった、石油ストーブの煙突を活用したもの。30Lの寸胴鍋いっぱいの枝葉を卓上コンロで加熱して、煙突部分で冷却して。初めての蒸留で取れた精油は5mlほどでした。
ーー30Lからたった5ml。気が遠くなりそうです。
澤田:最初はオイルだけで売ることができず、スプレータイプから販売を始めました。それでも初めて精油が取れた時は嬉しくて。「勾いがする!」って、夫と興奮したのを覚えています。
※水蒸気蒸留法とは、植物に水蒸気をあてて香り成分と水蒸気を混合させ、その後冷却することで蒸留水と精油に分離させる抽出方法。

ーー製品のこだわりはどんなところにありますか?
澤田:伐採からあまり時間が経っていない、フレッシュな枝葉を使っています。乾燥させた方がオイルは抽出しやすいのですが、トドマツのフレッシュな香りを届けたくて。1週間に1回くらいのペースで森に入り、自分たちで素材を集めています。
ーー枝葉の状態って、きっと時期によって変わりますよね?毎回同じ香りが出るものなのでしょうか。
澤田:おっしゃる通りで、毎回「全く同じ香り」にはならないんですよ。農作物と同じで、採取した時期や気候などによって若干甘めだったり爽やかさが強かったりします。
自然の中にあるものは、私たちがコントロールできる範疇を超えていると思うんです。
例えば植物から垂れる雫の一滴や、真冬の朝日を浴びてキラキラ光る雪の結晶。何も手を加えていないのに完璧な美しさだなって思うんですよね。
小さくて美しくて完璧なものが自然にはある。だから精油にもなるべく手を加えずに、「その時とれたもの」を活かして届けたいんですよね。

ーーラベンダーや柚子など、他のオイルとブレンドする際に意識されていることはありますか?
澤田:トドマツの香りはライトでブレンドしやすいので、ミックスした時にどんな香りにしたいのか。「色」や「質感」といったイメージを使いながら、トップ・ミドル・ベース※のバランスを意識して香りをデザインしています。
イメージを言葉にするのは夫で、形にしていくのが私の役割です。
※「トップ」「ミドル」「ベース」は、香りが時間とともに変化する際の3つの段階を示す言葉。トップノートは、つけた直後に香る最初の印象、ミドルノートは香りの中心となる部分、ベースノートは最後に残る香りで、それぞれの役割と持続時間が異なる。

自然との対峙と内省から生まれた「人と自然を繋ぐ」使命
精油づくりの中核を担う佳代子さんは、元看護師。HIKOBAYUの原点に通じる考えには、自然と対峙した体験があると言います。
澤田:もともと看護師として東京の急性期医療で働いていたのですが、次第に「命は救われるけど、その後の心身の健康の質が保てない」現実に違和感を抱くようになって。
病院を退職した後、僻地医療に興味が湧き、伊豆大島で3ヶ月ほど働きました。そこで初めて「自然への畏怖」を感じたんですよね。
ーーどんな体験だったのですか?
澤田:仕事終わりに一人で野草を取りに行ったんです。山の中を歩いている時にふと「ここに私がいることを誰も知らない」と気がついて。例えば足を滑らせたり、動物に襲われたりしても、誰にも気づかれない。自然と一人で対峙した初めての体験でした。

澤田:その後訪れたニセコで夫と出会い、2015年に地域おこし協力隊として夫婦で移住しました。
任期中に印象的だったのが農作物の「間引き」作業です。トレイに生えているたくさんの芽の中から、より生育の良いものを選び取らなければならない。私の指2本で終わってしまう命があるんだ・・って。
植物の命の力強さと儚さを感じた時に、「人の命も同じだな」って気づいたんですよね。医療現場で感じた人の命の力強さと儚さがリンクした出来事でした。
植物も人も同じ命で、「使命」を全うした時に終えるのだろうと。この時感じたことがHIKOBAYUの原点になっています。
ニセコに移住した当初は、白樺樹皮を使ったワークショップや、森でのフィールドワークなどの木育活動にも注力していたという佳代子さん。徐々に夫・健人さんが発案したクラフトアロマにも携わり、2017年に夫婦でHikobayuを創業。
しかし、創業当初は事業への葛藤があったと言います。
澤田:最初は「私はやりたくなかったのに」と、「夫がはじめた事業」と向き合うことから逃げていました。
アロマに興味があったわけでもないし、どちらかというと懐疑的だったんです。日本では精油は医薬品として扱われていないこともあり、「アロマなんて大丈夫?人の役に立つの?」と思っていました。

ーーまた看護師として働こうとは考えなかったのですか?
澤田:事業と並行して週1回、洞爺のホスピスで働いていたこともあったんですよ。下の子が生まれたばかりだったんですけど、1年半くらい続けました。
ーーすごいバイタリティーですね。
澤田:「医療現場にアロマが貢献できるんじゃないか」と思って行ったんです。
ちょうどアロマの勉強を始めて、自律神経への作用などエビデンスについても学び、「人の役に立てるんだ」と確信できた時期でもあったので。でも実際は、知識も経験も足りないと痛感しました。「もっと深く学ばなければ」と、事業に本腰を入れるきっかけになりましたね。医学博士に師事して、効果について学んだり。
自分が大切にしたいものを持ったままできることってなんだろう?と模索する中で、自分の価値観やありたい姿と事業が結びついていったんですよね。
私が大切にしたいのは、自然の流れとともに生きること。私たち人間も、自然のようにあるがままで、存在しているだけでいい。森が私に教えてくれたことを、HIKOBAYUを通して伝えていけばいいんだと思うようになりました。
香りは「今、ここ」にある豊かさを引き寄せてくれる
「以前は森にいるのが好きだったけれど、今はユーザーからの変化の声が一番嬉しい」と語る佳代子さん。今後をどのように見据えているのでしょうか。
ーー今後の夢や実現させてみたいことはありますか?
澤田:香りを通じて、「今、ここ」にある豊かさや幸せに気づく時間を増やせたらと思っています。
先日スキンケア品のテスト販売をしたのですが、ユーザーの方々から「スキンケアがほっとできる時間になった」「自分のための時間が取れていなかったと気づけた」といった声をいただいて。それがすごく嬉しかったんですよね。
情報社会の今、未来や過去のことに思考がいきがちな人が多いと思うんです。でも香りって「今」に引き戻してくれるんですよね。
ーー「今、ここ」を意識するってなかなか難しいのですが、香りを楽しむ数秒ぐらいはってことですよね。
澤田:深呼吸する、その瞬間を味わってほしいですね。
「今」にフォーカスした日々を積み重ねていくことで、「今回の人生良かったな」って終われると思うんです。「今」を感じられる五感を使った体験を、これからも届けていきたいです。

佳代子さんの感性の豊かさに心打たれた取材。人の命と真摯に向き合ってきたからこそ、自然も同じ目で見ることができるのだと感じました。
HIKOBAYUはこれからも森と人をつなぎながら、「今ここ」にある豊かさを届け続けます。
Information
合同会社Hikobayu(ヒコバユ)
〒048-1544
北海道虻田郡ニセコ町元町62-3